「住宅ローンを借り換えたい」「毎月の返済負担を減らしたい」と考えている方は多いのではないでしょうか。
住宅ローンの借り換えは、返済額の軽減や金利タイプの変更など、さまざまなメリットがあります。
しかし、「そもそも借り換えは契約してからいつでもできるの?」と疑問に思っている方も多いはず。
この記事では、住宅ローンの借り換えが可能になる時期やベストなタイミング、メリット・デメリットについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。賢い借り換えで、家計の負担を軽減しましょう。
住宅ローンの借り換えはいつから申し込める?金融機関による違い

住宅ローンを契約したばかりでも、より条件の良い商品を見つけたら、すぐに借り換えられるのでしょうか?
結論から言うと、住宅ローンの借り換えがいつから可能かは金融機関によって異なります。
一般的には「返済実績が1年以上あること」が条件となっていることが多いですが、金融機関によっては半年の返済実績で借り換えを受け付けるところもあれば、2〜3年の実績を求めるところもあります。
また、直近の返済状況も重要な条件となるため、延滞せずに返済を続けていることも大切です。金融機関ごとの違いや、自分の状況に合わせた最適な借り換えのタイミングを見極めることが、成功への第一歩となります。
金融機関ごとの借り換え可能時期の違い
住宅ローンの借り換えがいつから可能になるかは、借り換え先の金融機関によって条件が異なります。これは統一された規則がないため、各金融機関が独自に設定している申込要件に従う必要があるのです。
例えば、フラット35の借換融資では、次のような条件があります。
- 借り換え対象の住宅ローン契約日から申込日まで1年以上経過していること
- 申込日前1年間において延滞なく正常に返済していること
つまり、少なくとも1年間は現在の住宅ローンを返済し続ける必要があるということですね。もし直近1年以内に延滞があった場合は、その延滞を解消してから1年間経過するまで申し込めません。
一方で、民間金融機関では条件が異なる場合があります。例えば:
- A銀行:返済実績6ヶ月以上、直近6ヶ月間延滞なし
- B銀行:返済実績1年以上、直近1年間延滞なし
- C銀行:返済実績2年以上、直近2年間延滞なし
このように、金融機関によって返済実績の期間は6ヶ月から2年、時には3年と幅があります。そのため、「借り換えを考えている金融機関ではいつから申し込めるのか」を事前に確認することが重要です。
また、返済実績以外にも条件があることを忘れないでください。例えば:
- 年齢制限(申込時の年齢、完済時の年齢)
- 年収や勤続年数
- 団体信用生命保険への加入可否
これらの条件も金融機関によって異なるため、事前にチェックしておきましょう。特に年齢については、完済時の年齢が80歳未満などの制限がある場合が多いです。
PayPay銀行の住宅ローンでは、申込時の年齢が20歳以上65歳以下、完済時の年齢が80歳未満という条件があります。
一方、楽天銀行では申込時の年齢が20歳以上65歳以下、完済時の年齢が80歳以下となっています。細かい違いですが、高齢になってからの借り換えを考えている方は注意が必要ですね。
現在の住宅ローン契約から日が浅い場合、「A銀行なら半年で申し込めるけど、B銀行は1年必要」といった状況もあり得ます。
条件の良い金融機関を見つけても、まだ申し込み条件を満たしていない場合は、条件を満たすまで待つか、他の条件の良い金融機関を探すかの判断が必要になります。
自分の状況(返済実績や延滞履歴の有無)を正確に把握した上で、複数の金融機関の条件を比較検討することをお勧めします。
住宅ローンの借り換えは一度きりでなく、将来的に何度でも行える可能性があるので、焦らず最適なタイミングを見極めることが大切ですよ。
借り換えに最適なタイミングはいつ?
住宅ローンの借り換えは、いつでも行えば得をするというものではありません。最大限のメリットを得るためには、最適なタイミングを見極めることが重要です。では、どのようなタイミングが借り換えに向いているのでしょうか?
金利が下がったとき
まず最も重要なのは、金利環境の変化です。現在の住宅ローン金利が契約時より大幅に下がっていれば、借り換えで大きなメリットが得られる可能性があります。
例えば、10年前に3.0%で借りた住宅ローンが、現在なら1.0%で借りられるとすれば、金利差は2.0%もあります。
2023年から2024年にかけての住宅ローン市場では、変動金利が0.4〜0.6%台、10年固定金利が1.3〜1.6%台という水準が多く見られました。
もし5年以上前に住宅ローンを組んでいて、金利が2%を超えているなら、借り換えを検討する価値は十分にあるでしょう。
具体的な効果を見てみましょう。例えば、以下のケースを考えてみます:
- 現在の借入残高:2,500万円
- 残りの返済期間:20年
- 現在の金利:2.5%
- 借り換え後の金利:1.0%
この場合、借り換えによって月々の返済額は約19,000円減少し、総返済額では約450万円も節約できる計算になります。金利差が大きいほど、節約効果も大きくなることがわかりますね。
固定金利特約期間が終了するとき
多くの住宅ローンでは、当初3年・5年・10年などの固定金利特約期間を設けています。この期間が終了すると、変動金利に切り替わったり、優遇金利が縮小したりして、返済負担が増える可能性があります。
例えば、住信SBIネット銀行の「当初期間引下げプラン」では、当初10年間は店頭金利から年1.2%の引き下げがありますが、11年目以降は年0.5%の引き下げになります。この場合、10年経過時点で金利が0.7%上昇することになり、返済負担が増加します。
固定金利特約期間終了の2〜3ヶ月前から借り換えの検討を始めれば、金利上昇前に新たな住宅ローンに乗り換えられる可能性が高まります。特約期間終了のタイミングは、借り換えを検討する絶好の機会と言えるでしょう。
ライフスタイルの変化前
転職や独立、結婚、出産など、大きなライフイベントの前にも借り換えを検討する価値があります。特に転職や独立は、住宅ローンの審査において勤続年数や安定収入の面でマイナス評価になる可能性があります。
例えば、大手企業に10年勤務した後に独立を考えている場合、独立前に借り換えを行った方が審査に通りやすいでしょう。
独立後は、事業実績が3年以上ないと審査が厳しくなる金融機関も多いためです。三菱UFJ銀行やみずほ銀行など大手銀行では、自営業者の場合、確定申告書2〜3年分の提出を求めることが一般的です。
また、出産や育児で一時的に収入が減少する前に借り換えを行うことも、審査上有利に働く可能性があります。年収が減少すると、借入可能額も減少するためです。
大切なのは、計画的に行動することです。ライフイベントの半年〜1年前から借り換えの検討を始め、余裕を持って手続きを進めることをお勧めします。
焦って無理な借り換えをするよりも、自分の生活設計に合わせた最適なタイミングを見極めることが、長期的な家計の安定につながります。
住宅ローン借り換えのメリットとデメリット

住宅ローンの借り換えには多くのメリットがありますが、同時にデメリットもあることを忘れてはいけません。
借り換えを検討する際は、双方をしっかり理解した上で、自分にとって本当に得になるのかを判断することが大切です。金利の低下だけでなく、返済条件の見直しや生命保険の保障内容の充実など、さまざまな観点から総合的に判断しましょう。
金利低下以外にもある借り換えのメリット
住宅ローンの借り換えを考える最大の理由は「金利が下がって返済額が減る」ことですが、それ以外にも重要なメリットがいくつかあります。金利低下以外のメリットも知っておくと、借り換えを検討する視野が広がりますよ。
金利タイプの変更が可能
借り換えのタイミングで、変動金利から固定金利へ、あるいは固定金利から変動金利へと金利タイプを変更できます。これは将来の金利リスクに対する自分の考え方に合わせて選択できる重要なメリットです。
例えば、当初変動金利で借りていたけれど、今後金利上昇が心配な場合、固定金利に切り替えることで返済額の増加リスクを回避できます。
逆に、固定金利で借りていたけれど、低金利が続くと判断すれば変動金利に切り替えることで、より低い金利での返済が可能になるかもしれません。
2023年から2024年にかけては、日本銀行の金融政策の転換に伴い、長い間続いた超低金利時代が終わりつつあるという見方があります。
このような金利上昇が予想される環境では、変動金利から固定金利への切り替えを検討する価値があるでしょう。
団体信用生命保険の保障内容を見直せる
住宅ローンを借りる際には、ほとんどの場合「団体信用生命保険(団信)」への加入が必要です。これは、ローン返済中に契約者が死亡や高度障害状態になった場合、残りの住宅ローンが保険金で返済される仕組みです。
借り換えの際には、新たに団信に加入し直すことになりますが、これは保障内容を見直す絶好の機会でもあります。最近の団信は保障内容が充実しており、次のようなタイプがあります:
- 三大疾病保障付き(がん、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になると保険金が支払われる)
- 八疾病保障付き(三大疾病に加え、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎などが対象)
- 就業不能保障付き(病気やケガで働けなくなった場合、一定期間の返済をカバー)
例えば、住信SBIネット銀行の「11疾病保障付き団信」では、三大疾病に加えて「八大生活習慣病」や「精神疾患」なども保障対象となっています。
auじぶん銀行の「全疾病保障付き団信」なら、病気やケガで就業不能になった場合の保障もあります。
より充実した保障を持つ団信に加入することで、将来の病気やケガによる家計へのリスクを軽減できる可能性があります。
ただし、保障内容が充実している団信ほど、住宅ローン金利に上乗せされる保険料相当分が高くなる傾向があることも覚えておきましょう。
返済期間の見直しができる
借り換えでは返済期間も見直すことができます。例えば、返済期間を延ばせば月々の返済額を減らすことが可能で、短期的な家計の負担を軽減できます。逆に、返済期間を短くすれば総返済額を減らせる可能性があります。
生活状況やライフプランに合わせて返済期間を調整できることは、借り換えの大きなメリットの一つです。
例えば、子どもの教育資金が必要な時期には返済期間を延ばして月々の返済額を抑え、収入が増えた時期には返済期間を短くして早期完済を目指すといった戦略も可能になります。
ただし、返済期間を延ばすと総返済額は増える可能性が高いため、単純に月々の返済額だけでなく、総返済額も考慮して判断することが大切です。
また、年齢制限もあるため、例えば60代で借り換える場合は、完済時の年齢制限(多くの金融機関では80歳未満など)を考慮する必要があります。
借り入れ条件の見直し
その他、借り換えでは以下のような条件も見直すことができます:
- ボーナス返済の有無や割合
- 繰上返済手数料の条件
- 返済方法(元利均等返済と元金均等返済)
例えば、当初はボーナス返済を設定していたけれど、ボーナスが不安定になったため毎月返済のみに変更したい場合や、頻繁に繰上返済を行いたいので手数料無料の住宅ローンに切り替えたい場合など、自分のライフスタイルや経済状況に合わせた条件に変更できます。
メガバンクでは繰上返済に手数料がかかることが多いですが、ネット銀行の多くは繰上返済手数料が無料です。住信SBIネット銀行やイオン銀行など、インターネットからいつでも繰上返済ができるサービスを提供している銀行も増えています。
このように、金利低下だけでなく、さまざまな観点から借り換えのメリットを考えることで、より自分に合った住宅ローンを選択することができるでしょう。
借り換え時の注意点と失敗しないためのポイント

住宅ローンの借り換えにはさまざまなメリットがある一方で、注意すべき点もあります。借り換えを検討する際に見落としがちなポイントや、失敗しないためのチェック項目を押さえておきましょう。
諸費用の発生に注意
借り換えを行う際には、新たな住宅ローンを組むのと同様に、さまざまな諸費用が発生します。主な諸費用には以下のようなものがあります:
- 既存ローンの一括返済手数料:0〜33,000円程度
- 抵当権抹消費用:1万円〜数万円
- 新規ローンの事務手数料:借入額の2.2%程度(例:2,000万円なら44万円)
- 保証料:一括払いの場合、借入額の2%程度(例:2,000万円なら40万円)
- 抵当権設定費用:登録免許税や司法書士報酬で数万円〜10万円程度
- 印紙税:借入額に応じて1万円〜6万円程度
例えば、残高2,000万円の住宅ローンを借り換える場合、合計で50万円〜100万円程度の諸費用がかかる可能性があります。
これらの費用を考慮せずに借り換えると、金利が下がっても諸費用分のコストを回収できず、かえって損をしてしまうことがあります。
諸費用を含めた実質的な効果を試算するには、借り換えシミュレーションを活用するとよいでしょう。
多くの金融機関のウェブサイトでは、諸費用を考慮した借り換えのシミュレーションツールを提供しています。住信SBIネット銀行やソニー銀行のシミュレーターは使いやすいと評判です。
具体的には、次のような点をチェックします:
- 現在の残債額と金利
- 借り換え先の金利
- 残りの返済期間
- 借り換えにかかる諸費用の総額
- 借り換えによる月々の返済額の変化
- 借り換えによる総返済額の変化
- 諸費用回収までの期間(損益分岐点)
延滞や健康状態が審査に影響
借り換えの際には、新規で住宅ローンを組む場合と同様に審査があります。この審査で重要なのは、現在の住宅ローンの返済状況です。過去の延滞があると、審査に通りにくくなります。
特に注意したいのは、直近1年間の返済状況です。多くの金融機関では、直近1年間に延滞がないことを借り換えの条件としています。
例えば、みずほ銀行では「直近1年間に延滞がないこと」、三井住友銀行では「現在の住宅ローンを正常に返済していること」という条件があります。
また、団体信用生命保険の加入審査も重要です。健康状態によっては、一般の団信に加入できず、審査基準が緩やかな「ワイド団信」などを選ぶ必要がある場合もあります。
その場合、金利が0.2〜0.3%程度上乗せされることが多いため、借り換えによるメリットが減少する可能性があります。
健康状態が不安な場合は、審査前に「仮審査」や「事前審査」を利用できる金融機関を選ぶとよいでしょう。これにより、本申込の前に審査の通過可能性を確認できます。
借り換えができないケース
以下のようなケースでは、借り換えが難しい、あるいはできない可能性があります:
- 同一金融機関内での借り換え:一般的に、同じ銀行の同じ住宅ローン商品への借り換えはできません。ただし、金利交渉は可能な場合があります。
- 住宅を賃貸に出している場合:住宅ローンは自己居住用が前提のため、賃貸に出している物件は一般の住宅ローンでは借り換えできません。
- 物件価値が大きく下落している場合:担保評価額が借入希望額を下回る「担保割れ」の状態だと、借り換えが難しくなります。築年数が古い物件や、不動産価値が下落したエリアの物件は注意が必要です。
- 返済負担率が高い場合:借り換え後の返済額が年収に対して高すぎる場合(年収の30〜35%を超える場合など)、審査に通らない可能性があります。
これらのケースに該当する場合は、事前に金融機関に相談するか、ファイナンシャルプランナーなどの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
借り換えのベストタイミングを逃さないために
借り換えのタイミングを逃さないためには、定期的に自分の住宅ローンの状況と市場の金利動向をチェックすることが大切です。特に以下のようなタイミングでは、積極的に借り換えを検討しましょう:
- 金利が大きく下がったとき
- 固定金利特約期間が終了する半年〜1年前
- ライフイベント(転職、独立など)の前
- 住宅ローン借入から3〜5年経過したとき(残高がまだ多く、金利低下の恩恵を受けやすい)
借り換えの検討を始める際には、複数の金融機関を比較することも重要です。金利だけでなく、団信の種類や諸費用の違いなども含めて総合的に判断しましょう。モゲチェック、価格.comの住宅ローン比較などのサービスを活用すると、効率よく比較できます。
Q&A:住宅ローン借り換えに関するよくある質問

住宅ローンの借り換えについて、よくある質問にお答えします。実際に借り換えを検討する際の参考にしてください。
Q1:借り換えで得するための金利差はどれくらい必要ですか?
A1:一般的には、現在の金利と借り換え先の金利の差が0.5%以上あれば検討する価値があると言われています。ただし、借入残高や残りの返済期間、諸費用によっても変わります。例えば、残高が大きく(2,000万円以上)、残りの返済期間が長い(15年以上)場合は、0.3%程度の金利差でも借り換えのメリットが出る可能性があります。逆に、残高が少なく返済期間が短い場合は、1.0%以上の金利差がないと諸費用を回収できないことも。借り換えシミュレーションで具体的に計算してみることをお勧めします。
Q2:借り換えの申し込みから実行までどれくらいの期間がかかりますか?
A2:一般的に、借り換えの申し込みから実行までは1〜2ヶ月程度かかります。ネット銀行の場合は比較的早く、最短で3週間程度で完了することもありますが、地方銀行や信用金庫などでは2〜3ヶ月かかることもあります。審査期間(2週間〜1ヶ月)、必要書類の準備(1〜2週間)、契約手続き(2週間〜1ヶ月)を考慮して、余裕を持ったスケジュールを立てることをお勧めします。特に固定金利特約期間の終了に合わせて借り換える場合は、3〜4ヶ月前から動き始めるとよいでしょう。
Q3:借り換えのために必要な書類は何ですか?
A3:借り換えに必要な書類は、新規の住宅ローン契約時とほぼ同じです。主な必要書類には以下のようなものがあります:
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入証明書(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
- 現在の住宅ローンの返済予定表や残高証明書
- 不動産の権利証(登記識別情報)または登記事項証明書
- 住民票
- 健康保険証(団体信用生命保険の加入に必要)
- 印鑑証明書 金融機関によって細かい違いがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
Q4:住宅ローンの借り換えをすると、住宅ローン控除はどうなりますか?
A4:住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、借り換えをしても継続して受けられる場合があります。ただし、借り換え前の住宅ローン残高を超える金額で借り換えた場合、超過分については控除の対象外となります。例えば、現在の住宅ローン残高が2,000万円なのに、リフォーム資金などを含めて2,200万円で借り換えた場合、200万円分は控除対象外です。また、控除期間(10年間や13年間など)は当初の住宅取得時から数えるため、借り換えによって延長されるわけではありません。具体的なケースについては、税理士や金融機関に相談することをお勧めします。
Q5:借り換えをしても住宅ローンの繰上返済はできますか?
A5:もちろんできます。むしろ、繰上返済がしやすい条件の金融機関に借り換えることで、より効率的に住宅ローンを返済できる可能性があります。借り換え先を選ぶ際は、繰上返済の条件(手数料の有無、最低返済額、インターネットからの手続きの可否など)もチェックポイントの一つです。例えば、メガバンクでは繰上返済に手数料がかかる場合が多いですが、ネット銀行では無料のところが多いです。また、最低返済額も金融機関によって異なり、1万円からできるところもあれば、10万円以上からというところもあります。自分の返済計画に合った条件の金融機関を選びましょう。







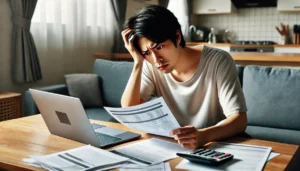
コメント