賃貸アパートやマンションに長年住んでいると、畳がボロボロになってきて「これって退去時に自分が払うことになるの?」と不安になりますよね。
実際、畳の張り替え代って結構な金額になるので、突然請求されたらびっくりしてしまいます。
でも安心してください。畳がボロボロになった原因や住んでいた期間によって、費用負担が変わってくるんです。
国土交通省のガイドラインに基づいて、どんな場合に自己負担になるのか、どうすれば余計な費用を払わずに済むのかを、分かりやすく解説していきますね。
賃貸の畳がボロボロになる原因と責任の所在

「畳がボロボロになったのは本当に自分のせい?」そんな疑問を持つのは当然です。
畳の劣化には色々な原因があって、それぞれで責任の所在が変わってきます。自然な経年劣化なのか、それとも使い方に問題があったのか。
この違いを理解することが、退去時の費用負担を左右する重要なポイントになります。
自然な経年劣化による畳の傷み
畳は天然素材でできているので、どうしても時間が経てば劣化していきます。普通に生活しているだけでも、日光による日焼けや湿気による変色、い草の摩耗などは避けられません。
特に6畳一間のような狭いお部屋だと、同じ場所を何度も歩くので、どうしても特定の部分がすり減ってしまうんですね。
また、梅雨時期の湿気や冬場の乾燥も畳には大敵です。窓際の畳が色褪せしたり、端がめくれてきたりするのも、ごく自然な現象と言えるでしょう。
こうした「普通に住んでいれば起こる劣化」については、基本的に借主の責任ではありません。
国土交通省のガイドラインでも、経年劣化や通常損耗は「賃料でカバーされるべきもの」と明記されています。
つまり、15年や20年住んでいて畳がボロボロになったとしても、それが自然な劣化であれば費用負担をする必要はないということです。
借主の責任となる畳の損傷パターン
一方で、明らかに借主の過失や不注意によって畳が傷んでしまった場合は、修繕費用を負担する必要があります。
例えば、タバコの火を落として焦げ跡ができた場合や、コーヒーやジュースをこぼしてシミを作ってしまった場合などですね。
また、ペットを飼っていて、おしっこの臭いが染み付いてしまったり、爪でひっかいて深い傷をつけてしまったりした場合も、借主の責任になります。
引っ越し作業で重い家具を引きずって畳に跡をつけてしまうのも、注意不足として扱われることが多いです。
さらに、カビが大量発生している場合は要注意です。適切な換気や掃除を怠っていたと判断されると、借主負担になる可能性があります。
特に気をつけたいのは、畳の上にずっと重いものを置きっぱなしにしていた場合です。
冷蔵庫や本棚、ピアノなどの重量物を直接畳の上に長期間置いていると、畳がへこんでしまって元に戻らなくなることがあります。こうした場合は「通常の使用方法を超えた使用」として、修繕費用を請求される可能性が高くなります。
退去時の畳交換費用の相場と負担ルール

「実際に畳を交換するとなったら、いくらぐらいかかるの?」これは誰もが気になるポイントですよね。
畳の修繕には表替えと新畳への交換という2つの方法があって、それぞれで費用が大きく変わってきます。
畳修繕の種類と費用相場
畳の修繕方法は主に3つに分かれます。一番安いのが「裏返し」で、畳表をひっくり返して使う方法です。
ただし、これは傷みが軽微な場合にしか使えません。次が「表替え」で、畳表(い草の部分)だけを新しくする方法です。
そして最も高額なのが「新畳」への交換で、畳床から全て新しくする方法になります。
賃貸物件では、ほとんどの場合表替えで対応されることが多いですね。表替えの費用相場は、使用する畳表のグレードによって大きく変わります。
エコノミータイプなら1畳あたり5,000円から8,000円程度、スタンダードタイプだと8,000円から15,000円、高級なものになると2万円を超えることもあります。
賃貸物件の場合、大家さんは通常エコノミーからスタンダードタイプを選ぶことが多いので、6畳の和室なら全体で3万円から9万円程度の費用がかかると考えておけばよいでしょう。
国土交通省ガイドラインに基づく負担ルール
畳の修繕費用の負担については、国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が非常に重要な指針となります。
このガイドラインによると、通常の生活で生じる損耗や経年劣化については、賃料に含まれているものとして扱われ、貸主が負担すべきとされています。
つまり、普通に住んでいて畳がボロボロになった場合は、借主が費用を負担する必要はないということです。
ただし、このガイドラインには法的な強制力はないため、賃貸借契約書の内容が重要になってきます。
実際の運用では、畳の耐用年数も考慮されます。畳の法定耐用年数は約6年とされており、この期間を超えて住んでいる場合は、経年劣化による損耗がより強く認められる傾向があります。
例えば、10年以上住んでいて畳がボロボロになった場合、ほぼ確実に貸主負担となるでしょう。
退去時に畳代を請求されたときの対処法
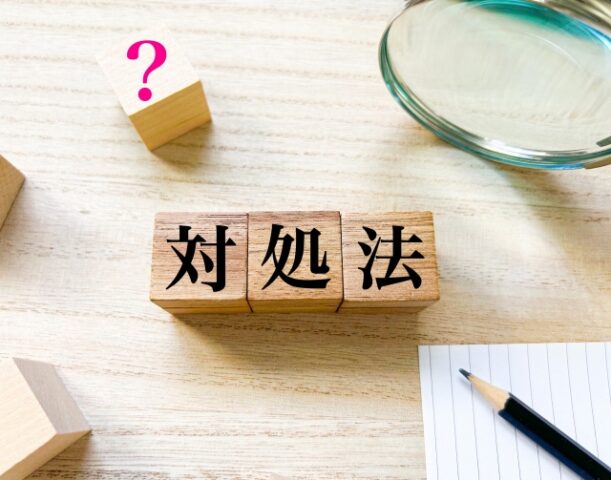
いざ退去の時になって「畳の張り替え代を負担してください」と言われたら、どう対応すればよいのでしょうか。
慌てて承諾してしまう前に、まずは冷静に状況を整理することが大切です。本来払う必要のない費用を請求されているケースも少なくありませんから、正しい知識を持って適切に対応したいものです。
ここでは、実際に費用請求された場合の具体的な対処手順と、トラブルを避けるために事前にできる準備について詳しく解説していきます。
まずは契約書と現状の確認
畳代の請求を受けたら、まず最初にやるべきことは契約書の内容確認です。賃貸借契約書や重要事項説明書に、畳の修繕に関する記載がないかチェックしましょう。
「借主が畳の表替え費用を負担する」といった特約があるかもしれません。もしそのような記載があったとしても、すぐに諦める必要はありません。その特約が妥当なものかどうか、後で検討することができます。
次に、現在の畳の状態を詳しく確認します。どの部分がどの程度傷んでいるのか、その原因は何なのかを客観的に判断することが重要です。
可能であれば、入居時の写真と比較してみてください。入居時の写真がない場合は、今からでも現状の写真を撮影しておきましょう。後々の交渉で証拠として役立つ可能性があります。
大家さんや管理会社との交渉術
不当と思われる請求に対しては、適切に交渉することが重要です。まず大切なのは、感情的にならずに冷静に話し合うことです。
「国土交通省のガイドラインでは、経年劣化による畳の傷みは貸主負担とされています」といった具体的な根拠を示しながら、丁寧に説明しましょう。
交渉の際は、以下のポイントを整理して臨むと効果的です。住居期間の長さ、畳の損傷状況とその原因、契約書の内容、国土交通省ガイドラインの該当部分などを資料として準備しておきます。
また、もし部分的な負担を求められた場合は、その根拠についても詳しく説明してもらいましょう。
第三者機関への相談も視野に
どうしても話し合いがまとまらない場合は、第三者機関への相談を検討しましょう。各自治体の消費生活センターでは、賃貸トラブルについて無料で相談を受け付けています。
また、法テラスや弁護士会の法律相談も活用できます。少額訴訟という手続きもありますが、これは最後の手段として考えておけば十分です。
多くの場合、適切な根拠を示して粘り強く交渉すれば、合理的な解決に至ることができます。重要なのは、一人で抱え込まずに専門家の意見を聞くことです。
よくある質問
- 賃貸で15年住んでいて畳がボロボロです。退去時の費用は自己負担になりますか?
-
15年という長期間の居住であれば、基本的に経年劣化の範囲内と判断される可能性が高いです。国土交通省のガイドラインでは、畳の法定耐用年数は約6年とされており、それを大幅に超えての居住なら貸主負担となることが一般的です。ただし、契約書に特約がある場合や、明らかな過失による損傷がある場合は例外となります。
- 畳の表替え費用はどのくらいかかりますか?
-
畳の表替え費用は、使用する畳表のグレードによって大きく異なります。エコノミータイプなら1畳あたり5,000円~8,000円程度、スタンダードタイプで8,000円~15,000円程度が相場です。賃貸物件では通常エコノミータイプが使用されることが多いため、6畳間なら全体で3万円~5万円程度を目安にしてください。
- 畳にカビが生えてしまった場合、退去時の費用負担はどうなりますか?
-
カビの発生原因によって判断が分かれます。建物の構造的な問題による湿気が原因の場合は貸主負担となることが多いです。一方、適切な換気や掃除を怠ったことが原因と判断された場合は、借主負担となる可能性があります。日頃から適切な湿気対策を行い、カビを予防することが重要です。
- 退去時に畳代を請求されました。どう対処すればよいですか?
-
まず契約書の内容と現在の畳の状態を確認しましょう。住居期間、損傷の原因、契約書の特約条項などを整理して、国土交通省のガイドラインに基づいて冷静に交渉することが大切です。話し合いがまとまらない場合は、消費生活センターや法テラスなどの第三者機関に相談することをおすすめします。
- 畳を長持ちさせるにはどうすればよいですか?
-
日常的な正しいお手入れが最も重要です。掃除はい草の目に沿って行い、水拭きは避けて乾拭きを基本としましょう。湿気対策として定期的な換気を心がけ、重い家具の下にはパッドを敷いて畳への負担を軽減することも大切です。これらを実践することで、退去時のトラブルを防ぐことができます。









コメント