「住宅ローンの融資額を増やしたいから親子共有名義にしようかな」「親と共同で不動産を購入するメリットってあるの?」と考えていませんか?
親子で共有名義にすれば住宅ローンの借入額が増やせるなどのメリットがありますが、実はあまり知られていないデメリットも存在します。
この記事では、親子共有名義のデメリット7つとメリット3つ、そしてデメリットへの対処法を専門家の視点からわかりやすく解説します。親子共有名義で不動産購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
親子共有名義で住宅を購入する場合の7つのデメリット
親子共有名義には、将来的なトラブルにつながる可能性のあるデメリットがいくつもあります。主なデメリットは以下の7つです。
- 親が亡くなった後、子の負担が増える
- ローンを滞納すると他の共有者にしわ寄せがいく
- 相続問題が複雑になる
- 離婚すると財産分与が複雑になる
- 相続税か生前贈与かの税金問題
- 維持費や固定資産税の分担が必要になる
- 修繕には全員の合意が必要になる
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
デメリット①:親が亡くなった後、子の負担が増える
親子共有名義でローンを組む場合、「ペアローン」か「リレーローン」のどちらかの形式になります。リレーローンの場合、親が亡くなると、残りのローンを子どもが引き継ぐことになります。
たとえば、5,000万円の住宅ローンを次のように分担していたとします。
- 親:20年で3,000万円(年間150万円)
- 子:20年で2,000万円(年間100万円)
しかし、親が10年後に亡くなってしまうと、支払い状況は次のように変化します。
- 親:10年で1,500万円支払い済み
- 子:残り3,500万円を30年間で支払う必要がある
親が団体信用生命保険(団信)に加入していれば、親の死亡時に残りの債務が免除されることもありますが、すべてのケースでそうなるとは限りません。また、ペアローンであっても、連帯保証人になっていると、親の債務を引き継がなければならない場合があります。
デメリット②:ローンを滞納すると他の共有者にしわ寄せがいく
親子共有名義での住宅ローンは一般的に連帯債務型です。これは、共有者が連帯して債務を負うことを意味します。
例えば、子どもが何らかの理由(失業、病気など)で住宅ローンを支払えなくなった場合、その分の債務は親が負担することになります。逆も同様で、親が支払えなくなった場合は子が負担します。
これは、片方の経済状況が悪化した場合に、もう片方に大きな負担がかかることを意味します。最悪の場合、住宅を手放さなければならなくなる可能性もあります。
デメリット③:相続問題が複雑になる
親子共有名義の場合、親が亡くなると相続手続きが複雑になります。
例えば、父、母、子ども2人(兄と弟)の4人家族で、父と兄が不動産を1/2ずつ共有していたとします。この状況で父が亡くなると、父の持分(全体の1/2)は相続人である母と子ども2人で分割することになります。
具体的には、法定相続分に従うと次のようになります。
- 母:父の持分の1/2(全体の1/4)を相続
- 兄:自分の持分(1/2)に加えて、父の持分の1/4(全体の1/8)を相続→合計で5/8に
- 弟:父の持分の1/4(全体の1/8)を相続
このように、持分割合が複雑になり、共有者も増えてしまいます。相続人同士の関係性によっては、将来的に不動産の管理や処分をめぐってトラブルが発生するリスクが高まります。
デメリット④:離婚すると財産分与が複雑になる
親子共有名義の不動産があり、子(夫)が離婚する場合、財産分与が複雑になります。
財産分与とは、夫婦が離婚時に、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分ける制度です。通常、夫婦の共有財産は半分ずつ分けることが多いですが、親子共有名義の場合は計算が複雑になります。
例えば、6,000万円の不動産で、父親と子(夫)の持分割合が3/5:2/5の場合を考えてみましょう。
- 子(夫)の持分:6,000万円 × 2/5 = 2,400万円
この2,400万円が夫婦の共有財産として考えられるため、妻はその半分の1,200万円を請求できることになります。
ただし、住宅ローンが残っている場合はさらに複雑になります。住宅ローンの残債が財産価値を上回る場合、財産分与をしない方が有利なケースもあります。
デメリット⑤:相続税か生前贈与を選ぶ税金の問題
親子共有名義にする際に、親が子に資金援助をする場合、その援助額によっては贈与税の課税対象となります。また、親が亡くなった場合には、親の持分が相続税の対象になります。
相続税と贈与税のどちらが有利かは、資産額や家族構成によって異なります。例えば、相続税には次のような基礎控除があります。
相続税の基礎控除額の計算式: 3,000万円+(600万円×法定相続人数)
妻と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)になります。父親の資産が4,000万円であれば相続税の支払いはありませんが、それを超える場合は課税対象となります。
一方、生前贈与の場合、年間110万円までが非課税です。計画的に贈与すれば節税できる可能性もありますが、まとめて贈与すると高額な贈与税がかかることもあります。
税金面でどちらが有利かは、個別のケースによって異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
デメリット⑥:維持費や固定資産税の分担が必要になる
共有名義の不動産は、維持費や固定資産税の支払いも共有者の責任となります。持分の割合に応じて負担額を算出する必要があります。
一般的には、話し合いで代表者がまとめて支払い、後から他の共有者に請求する形が取られます。しかし、何らかの理由で親子関係がこじれると、これらの金銭的な問題がトラブルの種になることがあります。
固定資産税については、親子共有名義の場合「連帯納税義務」となります。代表者に納税通知書は1通のみ送付されますが、納税義務は全員にあります。誰かが納付すれば全員の納税義務が消滅しますが、内部での清算は別途必要になります。
デメリット⑦:修繕には全員の合意が必要になる
共有名義の不動産では、大規模な修繕や改築、増築などを行う際に、全共有者の合意が必要になります。
民法第251条では、共有物の管理に関する事項は、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決めるとされています。しかし、共有物の変更については、共有者全員の同意が必要とされています。
親子関係が良好な間は問題ありませんが、何らかの理由で関係がこじれた場合、必要な修繕すらできなくなる可能性があります。これは長期的に見ると、不動産の価値低下や居住環境の悪化につながる恐れもあります。
親子共有名義のデメリットへの4つの対処法

親子共有名義にはデメリットがありますが、状況によっては対処法もあります。主な対処法は以下の4つです。
- 共有持分でお金を借りる
- 共有持分を売却する
- 共有持分を放棄する
- 共有物分割請求を起こす
それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。
対処法①:共有持分でお金を借りる
あなたの共有持分については、他の共有者の同意なしに自由に処分する権利があります。つまり、共有者の親(または子)に相談せずに、自分の持分を担保にして融資を受けることが可能です。
ただし、共有持分を担保にした融資を取り扱っている金融機関は非常に限られています。専門的な金融機関や不動産投資に詳しい業者に相談する必要があるでしょう。
対処法②:共有持分を売却する
自分の共有持分を売却することも、他の共有者の同意なしに可能です。これにより共有関係から離脱することができます。
ただし、共有持分だけを一般の不動産市場で売却するのは難しいことが多いです。共有持分専門の買取業者に相談するか、他の共有者に買い取ってもらうことを検討するとよいでしょう。
共有持分を売却すれば、共有名義による制約やリスクから解放されます。ただし、市場価値より安く売却せざるを得ないことが多い点には注意が必要です。
対処法③:共有持分を放棄する
共有持分の放棄も選択肢の一つです。持分を放棄すると、その部分の所有権を手放すことになります。
ただし、持分放棄には以下のような点に注意が必要です。
- 放棄した持分は他の共有者に帰属する(民法255条)
- 放棄しても、それまでに発生した債務や責任からは逃れられない
- 放棄するには登記手続きが必要
持分放棄は、不動産の価値が負債を下回る場合や、維持費の負担が大きすぎる場合などに検討される方法です。ただし、安易に放棄すると損失が大きくなる可能性もあるため、専門家に相談することをお勧めします。
対処法④:共有物分割請求を起こす
共有関係を解消する最終手段として、「共有物分割請求」があります。これは民法第256条に基づき、共有関係の解消を裁判所に求める手続きです。
分割方法には主に以下の3つがあります。
- 現物分割:物理的に不動産を分割する
- 換価分割:不動産を売却し、その代金を分配する
- 価格賠償:一方が他方の持分を買い取る
共有物分割請求は法的手続きなので時間とコストがかかりますが、他の方法で解決できない場合の有効な選択肢となります。ただし、親子関係が完全に壊れる可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。
親子共有名義で住宅を購入する3つのメリット

親子共有名義にはデメリットがある一方で、メリットもあります。主なメリットは以下の3つです。
- 借入金額を増やせる
- 住宅ローンの期間を延ばせる
- 住宅ローン控除を人数分受けられる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット①:借入金額を増やせる
住宅ローンの限度額は、基本的に申込者の年収によって決まります。親子共有名義の場合、親と子の年収を合算して審査されるため、単独で借りる場合に比べて借入可能額が大幅に増えることがあります。
例えば:
- 子の年収400万円のみの場合:借入限度額約2,000万円
- 親の年収600万円、子の年収400万円の合算:借入限度額約5,000万円
このように、親子の収入を合わせることで、より高額な住宅の購入が可能になります。特に、子どもがまだ若く年収が低い場合や、都心部など住宅価格が高いエリアでの購入を考えている場合に大きなメリットとなります。
メリット②:住宅ローンの期間を延ばせる
多くの金融機関では、住宅ローンの完済時年齢を80歳未満などと設定していることが一般的です。親が高齢の場合、返済期間が短くなって月々の返済額が高くなってしまうことがあります。
親子共有名義でリレーローンを選択すれば、子どもの年齢を基準に返済期間を設定できるため、返済期間を長く取ることができます。
例えば:
- 親(60歳)だけでローンを組む場合:完済時年齢を75歳とすると返済期間は15年
- 子(35歳)とリレーローンを組む場合:返済期間は最長40年も可能
返済期間が長くなれば、その分月々の返済額を抑えることができ、家計の負担を軽減できます。
メリット③:住宅ローン控除を人数分受けられる
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に受けられる税制優遇措置です。年末時点でのローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。
親子共有名義の場合、それぞれが自分の負担分に応じて住宅ローン控除を受けることができます。
例えば、借入金3,000万円のケースを比較すると:
- 子一人での借入:年間控除額約21万円
- 親子共有での借入(子2,400万円、親600万円):合計年間控除額約21万円(子約17万円、親約4万円)
一見すると同じように見えますが、所得税額が控除の上限となるため、子どもの所得税が21万円未満の場合は、親子で分けた方が控除総額が大きくなる可能性があります。
まとめ:親子共有名義は慎重に検討を
親子共有名義には、借入金額を増やせる、返済期間を延ばせるなどのメリットがある一方で、将来的なトラブルにつながるデメリットも多くあります。特に、相続問題の複雑化、離婚時の財産分与の問題、修繕時の合意形成の難しさなどは、長期的に見ると大きな課題となる可能性があります。
親子共有名義を検討する際は、次のポイントを念頭に置くとよいでしょう。
- 将来のライフプランを考慮する:婚姻、離婚、相続など将来起こりうる変化を想定する
- 契約内容をしっかり確認する:ローンの種類や団信の加入有無など、契約内容を把握する
- 専門家に相談する:税理士や弁護士など専門家のアドバイスを受ける
- 親子でしっかり話し合う:将来のトラブルを避けるため、親子で十分に話し合い、合意形成を図る
親子共有名義は、適切に利用すれば大きなメリットがありますが、デメリットやリスクも理解した上で判断することが重要です。お金が絡む問題だからこそ、感情的にならず、冷静に判断することが大切です。
特に親子関係は、他の関係以上に感情が入りやすいものです。将来的なトラブルを避けるためにも、契約前にメリット・デメリット双方を十分に理解し、親子でしっかりと話し合うことをお勧めします。







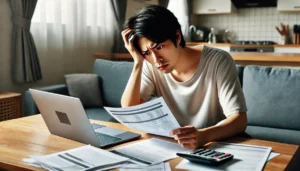
コメント