友人や知人にお金を貸したものの、約束の返済日を過ぎても返してもらえない…そんな経験はありませんか?
「催促しづらい」「関係が悪くなるのが怖い」といった気持ちから、つい放置してしまいがちですが、適切な対応をすれば円満に解決できる可能性は十分にあります。
この記事では、お金を返さない人の特徴から始め、効果的な対処法や法的手段まで、段階を追って解説します。あなたの大切なお金を取り戻すためのヒントを見つけてください。
お金を返さない人によくある特徴と心理

お金を返さない人には、いくつかの共通した特徴や心理パターンがあります。こうした特徴を理解しておくことで、今後の貸し借りで注意すべき人を見極めやすくなりますし、すでに貸してしまった場合も、相手の心理に合わせた効果的なアプローチが可能になります。
返済を促す際のコミュニケーション方法を工夫することで、成功率を高めることができるでしょう。まずは、お金を返さない人の特徴と、その背景にある心理状態をしっかり把握しておきましょう。
返済しない人に共通する特徴とその心理パターン
お金を返さない人には、いくつかの共通点があります。意外にも、それは単純に「悪い人だから」というわけではないことが多いんです。まずは典型的な特徴を見ていきましょう。
時間にルーズ
「時間にルーズ」な傾向が強い人は、約束した返済期日を守らないことが多いです。
こういった人は、他の約束事にも遅れがちだったり、期限を守れなかったりする傾向があります。遅刻が多い、提出物の期限を守れない、急な予定変更が多いなどの特徴があれば注意したほうがいいでしょう。
計画性がない
また「計画性がない」人も要注意です。お金の管理が苦手で、収入と支出のバランスが取れていない場合が多いです。たとえ返す意思があっても、実際のお金のやりくりができず、結果的に返済できないというパターンです。
LINEペイやPayPayなどのスマホ決済やクレジットカードで頻繁に支払う一方、現金がないと言っている人は、こうしたタイプかもしれません。
責任感の薄さ
「責任感の薄さ」も大きな特徴です。物事の優先順位づけが上手くできず、借金の返済よりも自分の欲しいものを買ったり、趣味にお金を使ったりしてしまいます。
SNSで遊んでいる様子や買い物をしている投稿があるのに、あなたへの返済は後回しにされているのであれば、この特徴に当てはまるでしょう。
返済する気がない
そして最も厄介なのが「返済する気がない」タイプです。最初から返す意思がなく、友情や親しさに付け込んでお金を借りる人もいます。
こういった人はしばしば「困っている」と訴えながらも、実際には他の用途にお金を使っていることもあります。
初めからこのタイプだと見抜くのは難しいですが、過去に他の人にも同様のことをしている場合があるので、共通の知人から情報を得ることも有効です。
さらに、最近増えているのが「経済的困窮」を理由に返せないケースです。コロナ禍の影響や景気の悪化で、本当に返したくても返せない状況に陥っている人も少なくありません。
このように、お金を返さない理由はさまざま。相手のタイプを見極めることで、より効果的なアプローチができるようになりますよ。
例えば、計画性のない人には分割払いの提案が効果的だったり、経済的に困窮している人には柔軟な返済プランを提案したりすることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
お金を貸す前に、相手がこうした特徴を持っていないか観察してみることも大切です。日常生活での小さな約束事の守り方や、お金の使い方などから、ある程度予測できることもあります。
ある調査によると、個人間の貸し借りで最もトラブルになりやすいのは「友人・知人間」であることがわかっています。親しき仲にも礼儀あり、お金に関しては特に慎重な判断が必要なのかもしれませんね。
お金を貸す前に確認しておくべきこと
お金のトラブルは未然に防ぐのが一番です。誰かにお金を貸す前に、いくつかの重要なポイントを確認しておくことで、後々の問題を大幅に減らすことができます。
最も基本的なのは「書面での約束」です。友人や知人相手だと、口約束だけでお金を貸してしまいがちですが、これが最大のリスク要因になります。例えば1万円程度の少額でも、必ず借用書を作成しましょう。
借用書には以下の項目を必ず含めるようにします:
- 貸付日と金額
- 返済期限(いつまでに返すか)
- 返済方法(一括か分割か)
- 両者の氏名と住所、連絡先
- 署名・捺印
書面を交わすことで、お互いの認識のズレを防ぎ、後々「そんな約束はしていない」というトラブルを避けることができるんです。
家庭裁判所のデータによると、友人間の金銭トラブルで最も多いのが「約束内容の食い違い」だそうですよ。
次に確認すべきは「返済能力」です。いくら親しい間柄でも、相手の経済状況をある程度把握しておくことは重要です。
毎月の収入や他の借金の有無、生活状況などから、本当に返済できるかどうかを判断しましょう。「困っているから」という理由だけで安易に貸すのは避けたほうが無難かもしれません。
リスクが心配なら「担保の設定」も検討してみてください。高額な貸付の場合は特に有効です。例えば、相手の持っている価値のあるもの(時計やブランド品など)を預かっておくという方法があります。
もし返済されない場合は、その品物で代替するという約束をしておくのです。国民生活センターの相談事例では、担保を取ることで返済率が向上したケースが多く報告されています。
そして忘れてはならないのが「第三者の立会い」です。お金を貸す場面に共通の知人や友人に立ち会ってもらうことで、後々のトラブルを抑制できる効果があります。証人がいることで、相手も簡単に約束を反故にしにくくなるんですね。
これらの対策を取っていれば、万が一の場合にも法的な手段に訴える際の証拠となります。
最悪の事態を想定して準備しておくことが、実は最も賢明なアプローチなのです。日本司法書士会連合会の統計では、個人間の金銭貸借で証拠が明確なケースは解決率が80%以上になるそうです。
お金を返してもらうための段階的アプローチ

お金を返してもらうには、友好的な手段から少しずつ圧力を高めていくのが効果的です。
いきなり厳しい対応をすると、かえって相手が反発したり、関係が悪化して返済が滞る可能性もあります。ここでは段階的なアプローチについて解説します。
最初のステップは「やんわりとした催促」
まず最初のステップは「やんわりとした催促」です。LINEやメール、電話などで気軽に連絡してみましょう。
例えば「先日貸したお金のことだけど、返済の目処はついてる?」といった具合に、相手を責めるのではなく、状況を確認する口調で伝えるのがポイントです。
この段階では、相手が単に忘れていたり、気づいていなかったりするケースが意外と多いんです。貸したお金が返ってこない理由の約30%は「相手が返済を忘れていた」という結果が出ています。
「直接会って話をする」ステップ
それでも反応がない場合は「直接会って話をする」ステップに進みましょう。対面での会話は文面よりも相手に伝わりやすく、こちらの困り具合も伝えやすいメリットがあります。
この時、公共の場所(カフェなど)で会うのがおすすめです。落ち着いた雰囲気で「実は今月の家賃支払いが厳しくて…」など、あなた自身の状況を伝えることで、相手も返済の必要性を感じやすくなります。
「内容証明郵便」というステップ
それでも解決しない場合は、「内容証明郵便」という少し公式な手段に移ります。内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便です。
法的手続きの第一歩として有効で、これが届くと相手も事の重大さを認識します。郵便局の窓口やオンラインで手続きでき、費用は500円程度からです。
さらに、「分割払いの提案」も効果的な方法です。「一括で返せないなら、月5,000円ずつでもいいから返してほしい」といった妥協案を示すことで、相手の負担を減らし、少しずつでも回収を始められます。
分割払いの提案をすることで約60%のケースで何らかの返済が始まったというデータもあります。
それでも進展がない場合は、「第三者を介入」させる方法もあります。共通の友人や知人に間に入ってもらうことで、当事者同士では言いづらいことも伝えやすくなります。
ただし、この方法は人間関係を複雑にする可能性もあるので、信頼できる人を選ぶことが重要です。
お金を回収するための法的手段
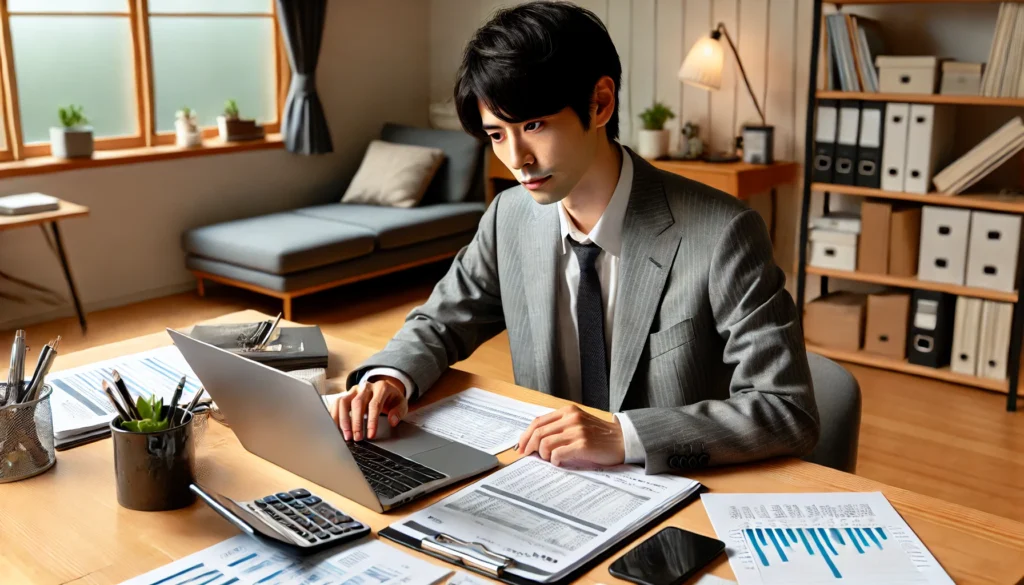
友好的なアプローチでも解決しない場合、法的手段を検討する時期です。
法的手段は「最終手段」というイメージがありますが、実は比較的利用しやすいものから段階的に進められるようになっています。ここでは主な法的手段について解説します。
最も手軽な法的手段が「支払督促」
まず最も手軽な法的手段が「支払督促」です。これは裁判所から相手に支払いを促す公的な書類を送ってもらう手続きです。
簡易裁判所に申立てをすると、裁判所が相手に「支払督促」という書類を送付します。
費用も比較的安く、訴訟を起こす場合の半額程度(例えば10万円の請求なら1,000円程度)で済みます。手続きも比較的簡単で、裁判のように出廷する必要もありません。
支払督促が届いた相手が2週間以内に異議を申し立てなければ、「仮執行宣言」が付き、さらに2週間異議がなければ確定します。
確定した支払督促は、判決と同じ効力を持ち、相手の財産を差し押さえる「強制執行」も可能になります。東京簡易裁判所のデータによると、支払督促のうち約40%は異議なく確定するそうです。
ただし、相手が異議申立てをすると通常訴訟に移行するため、その準備も必要です。「債務者が異議を出すことを見越して、最初から訴訟を選ぶケースも多い」とのことです。
60万円以下の請求なら「少額訴訟」
次に「少額訴訟」という方法があります。60万円以下の請求に限定されますが、通常の訴訟より簡易的で、原則として1回の審理で判決が出ます。
申立ては簡易裁判所で行い、費用は請求額に応じて異なりますが、10万円の請求なら2,000円程度です。
少額訴訟のメリットは、短期間(通常1〜2ヶ月程度)で解決できることと、手続きが比較的簡単なことです。最高裁判所の統計によると、少額訴訟の約85%は原告(お金を貸した側)の勝訴で終わるとされています。
より高額な請求を求める場合は「通常訴訟」
より高額な請求や、より強い法的効力を求める場合は「通常訴訟」を検討します。60万円を超える請求は通常訴訟になりますが、140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所での手続きになります。
費用は少額訴訟より高くなり、10万円〜数十万円程度かかることもあります。また、弁護士に依頼すれば、さらに費用がかかります。
通常訴訟は複数回の審理が必要で、解決までに半年〜1年以上かかることもありますが、判決の効力は強く、強制執行も可能です。
「訴訟まで進むと、相手も事の重大さを認識して和解に応じるケースが増える」とのことです。
最も穏便な法的手段は「民事調停」
最も穏便な法的手段としては「民事調停」もあります。これは裁判官と民間人の調停委員が間に入り、話し合いで解決を目指す方法です。申立ては簡易裁判所で行い、費用は少額訴訟とほぼ同じです。
調停のメリットは、裁判より手続きが簡単で、当事者の関係を悪化させにくいことです。
調停が成立すれば、その内容は裁判の判決と同じ効力を持ちます。日本司法書士会連合会の統計では、民事調停の約60%が合意に至るという結果が出ています。
最終的に判決や調停などで勝訴・成立しても、相手が支払わない場合は「強制執行」という手段があります。これは裁判所を通じて、相手の財産(預金、給与、不動産など)を差し押さえる手続きです。
強制執行を申し立てる際には、相手の財産に関する情報が必要です。司法書士や弁護士に依頼すれば、財産調査のサポートも受けられます。預金口座が分かっていれば銀行口座の差押え、勤務先が分かっていれば給与の差押えなどが可能です。
これらの法的手段は、状況や金額によって最適なものを選ぶことが重要です。少額なら支払督促や少額訴訟、話し合いでの解決を望むなら民事調停というように、自分のケースに合った方法を選びましょう。
また、法的手段を取る前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは経験豊富で、最も効果的な解決方法をアドバイスしてくれるでしょう。
Q&A:お金の返済に関するよくある質問
Q1. 借用書がないケースでも返済を求めることはできますか?
A1. 借用書がなくても返済を求めることは可能です。ただし、お金を貸した事実を証明する証拠が必要になります。例えば、振込履歴やメッセージでのやり取り、第三者の証言などが証拠として役立ちます。「先月貸した3万円、いつ返せる?」というメッセージに対して「来月の給料日に返すよ」と返信があれば、貸し借りの事実を証明できる可能性があります。証拠がまったくない場合は回収が難しくなるので、貸す際には必ず何らかの形で記録を残しておきましょう。
Q2. 友人が音信不通になった場合、どう対処すべきですか?
A2. まずは複数の連絡手段(電話、メール、SNSなど)で連絡を試みましょう。それでも連絡が取れない場合は、共通の知人を通じて状況を確認する方法もあります。それでも連絡が取れないなら、内容証明郵便を送ることで法的な催促の記録を残せます。相手の住所が分かっている場合は、訪問するという手段もありますが、常識的な時間帯に行い、威圧的な態度は避けるべきです。最終的には探偵や弁護士に相談し、相手の所在確認や法的措置を検討することになります。
Q3. お金を返さない人に対して、警察は介入してくれますか?
A3. 基本的に、お金の貸し借りは「民事」の問題なので、警察は介入しません。ただし、最初から返す意思がなくお金を借りた場合は「詐欺罪」に該当する可能性があり、その場合は警察に相談できます。詐欺の立証は難しいため、通常は民事的な解決方法(内容証明郵便の送付、少額訴訟、支払督促など)を検討するのが現実的です。警察は「民事不介入の原則」に基づき、個人間の金銭トラブルには基本的に関与しないことを覚えておきましょう。
Q4. いつまでお金の返済を請求できますか?時効はありますか?
A4. 金銭債権には時効があります。2020年4月の民法改正により、個人間の貸し借りの時効は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のどちらか早い方になりました。例えば、2023年1月に返済期限を設定してお金を貸した場合、遅くとも2033年1月までには法的手続きを取る必要があります。ただし、内容証明郵便の送付や分割払いの合意があると時効が中断されるため、返済の可能性がある限り定期的に催促を行うことが重要です。
Q5. お金を返してもらうために、やってはいけないことはありますか?
A5. 感情的になりやすい問題ですが、以下の行為は法律違反となる可能性があるので絶対に避けましょう。
- 暴力や脅迫的な言動(恐喝罪になる可能性)
- SNSでの晒し行為(名誉毀損になる可能性)
- 深夜早朝の連絡や訪問(迷惑行為になる可能性)
- 勤務先への連絡(業務妨害になる可能性)
- 借用書の改ざん(文書偽造罪になる可能性)
むしろこうした行為をしてしまうと、立場が逆転して自分が訴えられるリスクがあります。どんなに腹立たしくても、法律の範囲内で冷静に対応することが結果的には早期解決につながります。







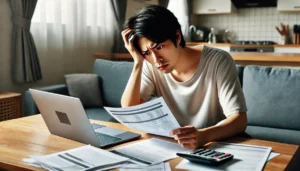
コメント