新しい教育制度である専門職大学。「大学と専門学校のいいとこ取り」という魅力的な制度ですが、実際に選択する前に知っておくべきデメリットもあります。
この記事では、専門職大学の基本情報を踏まえた上で、気になるデメリットについて詳しく解説します。進路選択の参考にしてください。
専門職大学とは?制度の概要とデメリットを考える前に

専門職大学は2019年4月にスタートした比較的新しい高等教育機関です。短期大学創設以来55年ぶりに国が作った新しい大学制度として注目されています。
4年制大学の学術的な教育と専門学校の実践的な教育を融合させた形で、産業界と連携した実践的な教育を特徴としています。
しかし、新しい制度である分、認知度の低さや実績の乏しさなど、いくつかの懸念点があるのも事実です。これから専門職大学を選択肢として考える方のために、具体的なデメリットを見ていきましょう。
専門職大学の基本的な特徴
デメリットを理解する前に、専門職大学の特徴をおさらいしておきましょう。
- 4年制(学士)と2年制・3年制(短期大学士)がある
- 卒業時に「学士(専門職)」「短期大学士(専門職)」の学位が取得できる
- 授業の1/3以上は実習・実技である
- インターンシップ等の実務実習が必須(4年制で600時間以上)
- 教員の4割以上は実務家教員
- 授業は原則40人以下の少人数制
専門職大学の5つの主なデメリット
専門職大学には様々なメリットがありますが、同時に気になるデメリットも存在します。これから詳しく解説する主なデメリットは以下の5つです。
- 社会的認知度の低さと評価の不確かさ
- 学費の高さと経済的負担
- 選択肢の少なさと地域的な制約
- 実績・就職データの乏しさ
- 特定の学習スタイルに合わない可能性
1. 社会的認知度の低さと評価の不確かさ
専門職大学の最大のデメリットは、まだ社会的な認知度が低いことです。教育関係者でさえ「名称だけは知っている」という人が多く、その内容まで理解されていないのが現状です。
高校教員を対象としたアンケート調査では、「名称だけは知っている」と答えた教員が約4割に上りました。制度を知っていても、その内容までは理解されていないというのが現状です。
企業の採用担当者や一般社会では、さらに認知度が低い可能性があります。「専門職大学卒」というと、単なる専門学校と誤解されたり、一般の4年制大学と比べて低く評価されるリスクがあります。
ある専門職大学の学生の声によると、「世間的にはFランや専門学校と同等に扱われることが多い」という指摘もあります。大卒資格を得ても、それに見合った社会的評価が得られない懸念があるのです。
2. 学費の高さと経済的負担
専門職大学は、実習や実技を重視するカリキュラムのため、一般の大学と比較して学費が高額になる傾向があります。特に私立の専門職大学では、4年間で1,000万円近い学費がかかるケースもあります。
実習設備や少人数教育のための施設維持費が必要なため、このような高額な学費設定になっているようです。奨学金は利用できますが、卒業後の返済負担を考えると、経済的なデメリットは無視できません。
一方で、専門学校と比較すると、専門職大学は4年間のカリキュラムになるため、早く社会に出て稼ぎたい人にとっては時間的・経済的なコストが高くなります。
3. 選択肢の少なさと地域的な制約
2021年5月時点での専門職大学の設置校数は、専門職大学14校(公立2校、私立12校)、専門職短期大学3校(公立1校、私立2校)と非常に限られています。
令和3年現在の専門職大学設置校数は、専門職大学14校(公立2校、私立12校)、専門職短期大学3校(公立1校、私立2校)となっています。一般的な大学や専門学校と比べるとまだまだ数は少ないのが現状です。
これは一般の大学や専門学校と比べると圧倒的に少なく、自分の興味ある分野の専門職大学がなかったり、地理的に通学困難な場合もあります。
また、多くの専門職大学が単科大学であるため、入学後に興味が変わっても学部・学科の変更や転部が難しいという制約もあります。
4. 実績・就職データの乏しさ
専門職大学は2019年にスタートしたばかりの制度であるため、卒業生の就職実績や進路データがまだ十分に蓄積されていません。企業での評価や長期的なキャリア形成における効果も未知数です。
第一期生が卒業したとしても、その後のキャリアパスや昇進、転職などの長期的なデータはまだありません。これは進路選択において大きな不安要素となります。
専門職大学は実践的な教育により即戦力となる人材を育成することを謳っていますが、それが実際の就職市場でどう評価されるかはまだ明確ではありません。特に社会的地位や給与面での評価は、今後の卒業生の実績にかかっています。
5. 特定の学習スタイルに合わない可能性
専門職大学の教育スタイルは、アクティブラーニングや少人数制のクラス授業が中心となっています。
これは積極的に発言したり、グループワークを好む学生には適していますが、一人で黙々と学習するタイプの学生には苦痛になる可能性があります。
専門職大学は社会で活躍できる即戦力を育てるために、実践的な教育を多く取り入れています。アクティブラーニングは話し合いや発表が好きな人には向いていますが、人見知りの学生にとっては成績を残しにくいという声もあります。
また、40人以下の少人数クラス制は、教員と学生の距離が近いというメリットがある一方で、人間関係のトラブルに巻き込まれやすく、精神的負担が大きくなるケースもあります。
専門職大学を選ぶ際に考慮すべきポイント
デメリットを踏まえた上で、専門職大学を選ぶ際に考慮すべきポイントをご紹介します。
どんな人に向いているか
専門職大学は以下のような人に向いているでしょう。
- 明確な職業目標を持っている人
- 実践的な学びを重視する人
- グループワークや発表などのアクティブラーニングが好きな人
- 専門分野のリーダーを目指したい人
- 大卒の資格と実践的スキルの両方を求める人
逆に、以下のような人には向かないかもしれません。
- 一人で静かに学習するスタイルを好む人
- 幅広い教養を身につけたい人
- 学費の負担を最小限にしたい人
- 短期間で就職したい人
- 卒業後の進路に社会的評価を重視する人
情報収集と比較検討の重要性
専門職大学を選ぶ際は、以下のポイントを重視して情報収集することをお勧めします。
- カリキュラム内容: 実習や実技の具体的な内容、理論学習とのバランス
- 教員構成: 実務家教員の実績や経歴
- 施設・設備: 実践的な学びをサポートする環境
- 連携企業: インターンシップ先や共同研究を行う企業の質と量
- 学費と奨学金: 総額コストと支援制度
- アクセス: 通学のしやすさ、生活環境
また、専門職大学と一般大学、専門学校との比較も重要です。同じ分野を学ぶ場合、どの教育機関が自分の目標や学習スタイルに合っているかを多角的に検討しましょう。
まとめ:専門職大学のデメリットを理解した上での選択を
専門職大学は、実践的な職業教育と大学の学術的教育を融合させた新しい選択肢として注目されていますが、認知度の低さや実績の乏しさなど、いくつかのデメリットも存在します。
重要なのは、これらのデメリットを理解した上で、自分の目標や適性に合っているかを見極めることです。将来のキャリアを見据えて、専門職大学、一般大学、専門学校のそれぞれの特徴を比較検討し、最適な進路を選択しましょう。
専門職大学はまだ発展途上の教育制度ですが、今後社会的認知度が高まり、卒業生の実績が蓄積されれば、評価も変わってくる可能性があります。自分の将来のビジョンと照らし合わせながら、慎重に検討することをお勧めします。
悩んだ際は、複数の教育機関のオープンキャンパスに参加したり、在校生や教員と直接話す機会を設けるなど、できるだけ多くの情報を集めることが大切です。あなたにとって最適な選択ができることを願っています。
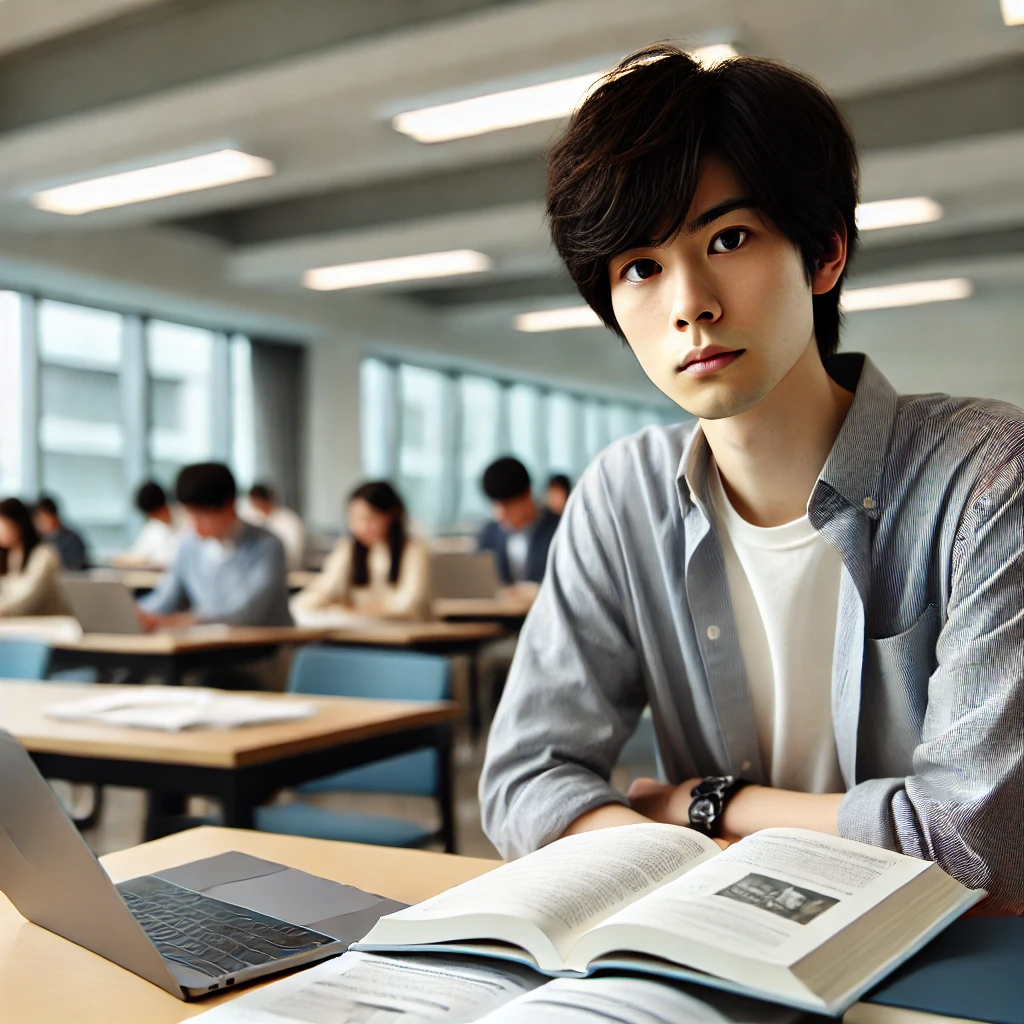








コメント